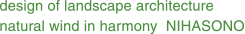H28年度住宅経済関連データのサイト(国土交通省)を見ると、既存住宅取引戸数は、微かに増えてはいるが、H5年からほとんど横ばい状態であると言っていいようなグラフだった。しかし新築着工数との割合でみれば、H25年度までのグラフは縮小しているが、おそらく今後は増える一方である。(新築が減少していくのだから当たり前か) 既存住宅を購入すれば、建物をリノベーションする場合もあるだろうし、そのまま敷地内(庭)をつくり直したくもなるのが流れかもしれない。
「リガーデン」ということばを聞くが「リフォーム」同様の造語、和製英語だ。renovation のほうがしっくりくるような気もするが、人によるのだろう。その「庭のつくりなおし」「庭の修繕」をする場合、拙い経験から、無駄なく、後悔しない提案をしてみたい。
1. 再利用できるものはなるべく使う、瓦礫さえも材料だ
エクステリアと呼ぶ製品たちは、設置したその日から劣化が始まってしまう。これは工業製品たる宿命のようなものなので、非難や批判するわけではない。外で野ざらしになっているものに、経年変化はどうしようもない。前の施主がつくったもので、時間のおかげで著しく見栄えが落ちているものは、撤去・交換するしかないが、処分するのは金属物だけにしておこう。その金属製品も、アルミと鉄材などに分ければ買い取ってもらえる場合もある。石材などは、処分場では引き取ってもらえないことがほとんどだ。馴染みの石材屋などに声をかければ、別な敷地で転用できるかもしれないが、それも時と運次第である。敷地によっては、重機が据えられなくて持ち出すのも不可能な場合がある。
そこで、再利用を考えよう。木製の造作物、コンクリート、石材などは、施工業者にハンマードリルや重機で手で持てる大きさに壊してもらい、別な用途に使うのである。見えないところ… 地面のなかの改善だ。
すでに庭にあるものは、積極的に改善材料につかおう。捨てられないからと埋めるだけでは「産業廃棄物処理法」にかかってしまう。(←ここ大事。プラン図、施工途中の写真などは残しておこう。有害物質が染み出すようなものも気をつけて。)

長年のあいだに踏み固められ、建物以上に酷使されたかもしれない庭は、見た目よりも通気性も浸透性も落ちていることが多い。四方がコンクリートで固められているようなところは尚更だ。そのままであれば、新たに植える樹木も草花も家庭菜園も、健全な生育をなさないことがありそうだ。新しくはじめる前に、まず落ち着いて、敷地内の地面の様子を確認してみよう。
晴れた日に、どれぐらい地面がしまっているかを、移植ゴテで感触を確かめるのもいい。ラクに移植ゴテが地面に入るのか? 跳ね返されるほど固いのか? 石が多いのか? 次に雨の日の状態を見てみよう。(引っ越して来る前に、地面の状態も見ておくのが理想だけど、そこまで気がまわることは稀。) 雨の日に確認することは、どれぐらいの量の水が流れているのか、どの方向へ向かって水が流れているか、敷地内のどこに水たまりができるのか(できないのが理想)、何日ほどで地面が乾くか、などなど。 例え上記の事柄のなかで、不安な箇所がなさそうでも、今後の庭の状態を健全に保つならば、現況よりもっと素早く浸透する地面を目指そう。敷地内の雨水を道路や他所に流さず、できるだけ地面のなかに浸透させよう。 敷地内に浸透させることで、好ましいことは大きく2点。
(1) 川を汚さない … 水といっしょに地表面の土・有機物が敷地の外まで流れ出し、それがいっきに下水から川に流れ込むことで、水かさが増え、そのうえ川が汚れてしまう。最近は集中豪雨が多いので、必要以上に川に水が集まるのは心配だ。しかしそれを各々の家で、できるだけ地面に浸透させてしまえば、自然災害が起こる割合も減るというものだ。
(2)敷地内の地面に、新鮮な水・空気がおくりこまれること … 水を浸透させることで、空気や養分もいっしょに地面に入り込み易くなる。樹木の根に酸素が必要なことは、なかなか気づきにくいことかもしれない。街路樹などの植栽基盤の改善にも、同じ考えをもとに施工がなされることが多い。街路樹、公園の樹木などで、樹勢が弱ってくるさまざまな原因のひとつに地面の問題がある。長年の踏圧や、幹の際ギリギリまで舗装する植栽基盤の狭さのために、根が呼吸困難を起こすことだ(呼吸のために葉で取り込んだ酸素を、樹木自身が根まで運ぶことはない)。水はけがよろしくない地面のため、雨後、地中の水がなかなか引かず、根が水に浸かった状態になり、根腐れを起こしてしまうこともある。これも呼吸できないことではいっしょだ。
では、出てきた瓦礫を再利用して、お庭を改善しよう。費用をかけて処分するより、ゴミに見えたものを一転、敷地内の通気と浸透・排水のための材料に変える。
改善し、まもなく土のなかで空気と水が動き出すと、目では同じ庭でも、肌で感じる空気感がやわらかい。朝、雨戸を開けた時や、夜にそよそよと入り混む風で、変化を感じるはずだ。森のなかのうっすらとした菌臭のような空気。(菌臭には鎮静作用があるという説もある)土中の微生物が活発になれば、発生する二酸化炭素の量が増えているはずなのに、そのやわらかい気持ちよさは何処からくるのであろうか。 コンクリートや石材は、どんなに壊しても大きな隙間ができるため、地中の浸透改善にはとても役立つ。もし既存の植栽を剪定する必要がある庭だったなら、その切った枝葉も土壌改善に使おう。細く浅い溝を掘って、枝を詰めていくだけでも水が流れやすくなり、地面の通気が変わる。瓦礫のあいだに入れるなら、植物と土をつなぐ菌も、より活発になるだろう。
みえない地中の環境を整えることは、庭のつくりなおしの基礎のようなところ。ここを疎かにすると、せっかくの素敵な樹木も、数年で枝の先が枯れるところが出たりして、樹形がくずれてきたりするのがつらいところ。だからといって、樹木を植えたあとでは、改善の施工は面倒だ。はじめに庭の状態を見て、よく考えよう。
※ 写真は、長年の踏圧で固く締まった地面に横溝を掘り、そのお庭で切った枝葉を詰めたところ
リガーデンネタ続く。 今後の予定
2.萌芽更新のすすめ
3.自然素材を多く
4.庭土の耕転
◇ 2023, 0622 修正
つくば、茨城のお庭屋 ニハソノ 自然を大事にする造園と外構
樹木医が提案するお庭プラン