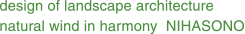人のけしきも、夜の火影ぞ、よきはよく、もの言ひたる声も、暗くて聞きたる、用意ある、心憎し。匂いも、物の音(ね)も、ただ夜ぞひときはめでたき。 「徒然草 第191段より抜粋」
陽が眩しい時に聞く蝉の声など、庭の暗がりから聞こえてくる蟋蟀の声ほど愛しくは感じない。夜に細く窓を開け、外の音を部屋のなかに引き込むと、虫の声が落ち葉の匂いと共に入ってくる。つくばのあたりでポピュラーなのが、エンマコオロギ、ハラオカメコオロギ、ミツカドコオロギ、クサヒバリ、カンタン、カネタタキなどであろうか。早春でも温かい夜には、クビキリギスの声もある。

庭のどこかに、放っておいた薮をつくったり、枝を強く透かしたりしないエリアを残したり、また、草を刈りとったとしても、その草を粗く積んだままにしておけば、鳴く虫たちの隠れ家にもなる。「…きれいにしておかないと近所の体裁が..」の義務感から、一本残らず根こそぎむしった地面は、そのときだけは気持ちもスッキリする。シンプルな空間は、シンプル故そこに豊かな意味が見えてくれば素敵だが、裸の地面に終わるだけでは殺風景だ。街じゅうが記号のような空間ばかりなら、整合性がとれて隣を安心させるが、その安心は「含みのある空間」からは、どうしても離れてしまうのかもしれない。
なにもないほうが、管理も手入れも要らずラクだ。しかし敷地のどこかに陰がある場所、一目で把握しきれない、見えない場所があると、使える面積は狭くなるが、含みがある分、イメージの庭は広くなる。そこは住む人の意識の「外」にある空間である。意識の外ゆえ、そこに何坪などという数字はない。そこはまさに自然と呼んでもいいのでは。雑草と呼んでしまう草が繁り、ちいさな生き物が遊ぶ。
もしかすると、自然が苦手な人の心の奥には、そのような場所がもつ特徴、「意識できないもの」への不安があるのかもしれない。管理できないものへの ” キモチワルサ ” か。庭は、のっぺりとした日常を少しだけ刺激させるときがある。それは意識の外からくる自然ではないだろうか。
せっかく手に入れた敷地を、右から左に隅々まで使い倒さないのはもったいない。必ずしも、決まった機能があることが使い倒すことではないだろう。放っておくことが、思いがけない機能を発揮するときもある。小さな生き物の住処になり、心地よくも季節を感じさせる虫の声が聞こえてくるようになるかもしれない。視覚だけはない、聴覚の快感を足元で気づいた途端に、自分の庭がイメージで何倍も広がるのである。そこから、子どもといっしょに図書館などで庭の虫の声を手掛かりに、コオロギやバッタ類を調べれば、その声の主を知ることになる。はじめは意識の外から来た虫の声であったのに、種類を知った後の虫の声は、身近な知り合いに変わるのを感じるだろう。ノイズでしかなかったものが、あれは誰々の声、これは誰々の声と人数(虫の種数 ? )まで聞き分けたりして微笑む子どもの顔はどうだろう。何とも和む一瞬ではないか。
庭を放ったらかしにしたときでも、その自分のだらしなさを理由づけできる。あたかも自分はその虫の声を愉しむために、あえて草むしりをしなかった、あえて枝を切り落とさなかった、とママに伝えよう。(納得されないか) 度が過ぎると「あなたの薮庭から蚊がやってきてどうにもならん。」と、お隣から苦情を言われるかもしれない。虫の音だの、夜の庭の豊かさだの、窓からはいる夜の風だのという、ささやかな愉悦はとんでしまうか。
◇ 2023, 0622 修正
ニハソノ ビオトープ計画管理士 1級
生きものがいる庭
子どもといっしょに探検するお庭、調べるお庭